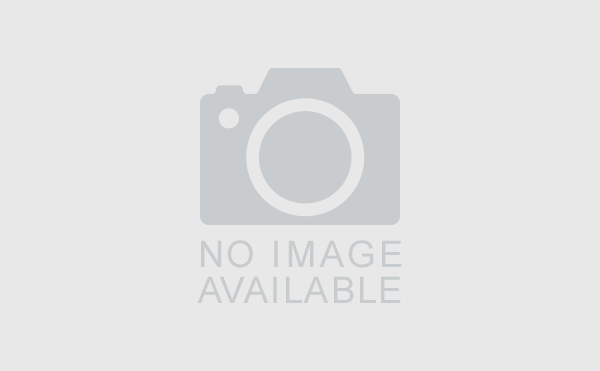ヨコハマタイワ35の記録(「宇宙人はいるのか?」SFについて)
昨日は「ヨコハマタイワ35」でした。会場は港の見える丘公園の近くのイギリス館という洋館でした。参加者の評判がいい割に安くてオススメ。
テーマは「宇宙人はいるのか?」。これは「SFっぽいテーマ」というお題で、事前に募集した中から決めたものです。
普段やらないテーマだったので参加者があつまるか少々不安でしたが、結果、7名参加で満員御礼。あと、提題者にも(強制?)参加いただき、計8名でした。
・・・
今回、あえて普段と違うテーマ設定をしたのには、二つの狙いがありました。
一つ目は、普段やらないような、SFっぽいテーマをやったらどうなるか実験したい、という狙い。
まず、こういうテーマだと100%男性だろう、という先入観があったのですが、結果、女性2名に参加いただきました。男女によってテーマの好みの違いがある、というのは偏見だったのかも、と思えたのは収穫でした。
そして、実際こういうテーマでやってみると、やはり「予想通り」、ある程度のSF的な素養がないと理解が難しい話になる、というのが発見でした。銀河の構造、四次元、素粒子などなど。
ただ、難しい話になるのは、参加者がそういう話を「したい」という強い思いがあるからなんですよね。普段できない話をできた喜びのようなものが参加者から感じられました。二時間という期間限定ではあるけど、この場が、「哲学」&「SF」という、二重にマニアックな興味を持ったマイノリティな人々の居場所になったのかも。なんて。(僕は「哲学者いちろう」を自任しているので、こういう場に関われたのはすごく嬉しいです。)
・・・
もう一つの、今回のテーマ設定の狙いは、進行役(つまり僕)や参加者とは別に、提題者という立場の人が加わったら、対話の場がどうなるのか実験したい、というものでした。
僕は、対話の場がなるべく平等になるよう気をつけているのですが、どうしても、参加者に比べて進行役が偉くなりがちです。(あと常連と初参加という違いも生じがち。)
更に、その場でテーマを決めるのでなく、事前に進行役(つまり僕)がテーマを決める流れだと、進行役&提題者としての僕の偉さは、更に強化されることになります。
このような状況に対し、提題者が加わったらどうなるのか、というのが今回の実験でした。
結果としては、狙い通り、進行役の偉さは緩和されたかな。今回、「宇宙人はいるのか?」という「メイン問題」の話を進めるにつれて、「宇宙人がいるかどうかを、どのように確かめるのか?」「宇宙人とはどのような存在なのか?」「知的生命体と(知的でない)ふつうの生命体の違いは?」といった、いくつかの「サブ問題」に分かれていきました。そこで、中盤で、そのうち、どの「サブ問題」で進めるのかを提題者に選んでもらいました。これでかなり進行役の偉さ&負担が緩和されました。(一方で、提題者の選択に参加者が従わなくてもいい、という自由さも重要なのですが。)
なかなかよかったので、今後も、たまにはこのスタイルでやってみようかな。
・・・
ということで、実際の対話の内容ですが、提題者の選択により、「宇宙人とはどのような存在なのか?」という方向で話が進みました。
精神体のようなものかも、四次元の存在かも、今は思いつくこともできないようなものかも、などなど。話が進むというよりは、どこまでも話が広がっていく感じ。
これはこれで楽しいけど、話が広がりすぎかな、と思っていたところ、また提題者に話を方向づけてもらって、「この世界に宇宙人は来ているのか?」という「サブサブ問題」に絞ってもらいました。
それでも、一旦火がついた想像力の翼は広がり続けて、上位存在としての宇宙人が地球を観察しているかも、地球人の一部は宇宙人の血が混じっているかも、などなど、更に話は広がっていきました。
ここで出た言葉の中で、僕の中でのお気に入りは「次元の間借り」。これは、宇宙人が、多次元構造を持つこの世界の「六次元目」を間借りしているかもしれないという話なのですが、宇宙人や多次元といった壮大な話と、間借りカレーみたいな生活的な言葉が結びついているのが、藤子・F・不二雄っぽくてよかったです。
あと、「地球人にとっての宇宙人とは、古代人にとっての別の大陸の人間みたいなもの」という話もよかったです。宇宙人というものの「わからなさ」をうまく掬い取っていると思いました。
(ほかにも、これだけじゃわからないかもだけど「生命=意思=知性=エネルギー ⇒ 宇宙人」というような壮大な話もありました。)
ということで、色々な話が出たのですが、この終盤での話の広がり方は、解き放たれた想像力というものの凄さを目の当たりにしたようで、ちょっと感動的でした。
・・・
だけど、参加者の一人がこだわっていて、最終盤で少し問題としたとおり、これほどの話の広がりは、「宇宙人がいるかどうかを、どのように確かめるのか?」という、「証明」や「確認」の問題を一旦棚上げすることで成立するものなんですよね。宇宙人について色々想像するのは楽しいけれど、「じゃあ、どうやって確認するの?」と問われれば、そこで話の盛り上がりは止まってしまう。
僕の考えでは、確認を重視すれば、それは社会にとって有意義な「科学」に近づいていく。一方で、確認なんてどうでもいい、と開き直れば、それは、想像力の爆発としての楽しい(けれど社会にとって有意義になりにくい)「哲学」(特に形而上学)に近づいていく。(だから、SFにも二種類あって、確認=サイエンス優位のSFと、想像力=フィクション優位のSFがあるのかも。)
なんていうことを考えることができたのは、「哲学者いちろう」としても収穫でした。
・・・
最後に、今回の反省点として、「宇宙人はいるのか?」というテーマ設定が広すぎた、という話がありました。確かにそうなんですよね。けど、対話の中で、提題者の、このテーマに対する熱い思いを聞くこともできて、変にテーマをいじってしまったら、提題者の思いを取りこぼしてしまう、とも感じました。難しいところですね。
・・・
ということで、個人的には、とても収穫があったのですが、まあ、たまにやるからいいような気もするので、次回は普通にやります。(今回のが形而上学だとしたら、普段の対話は倫理学的になりがちだと思うのですが、それはそれで楽しいんですよね。)